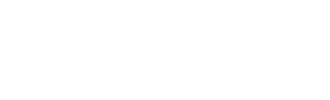今年度から初登場の数学ⅡBC。
最近は課程がコロコロ変わることから、”新課程”という言葉をもうあまり使いたくありません。
ⅡBからⅡBCになり単元も増え、それに伴い大問の数も多くなりました。
大問が7個は史上最多なのではないでしょうか?
もちろん、大問が増えたということは1個1個の内容は薄くなっているはず…?
何はともあれ、とにかく解いてみましょう。
以下に記す難易度は次の表を参考にしてください。
難易度
★☆☆:教科書レベル。
★★☆:チャート黄レベル。
★★★:チャートで対応しづらいレベル。
大問1
(1) 難易度 ★☆☆
単位円を利用した三角関数の方程式がテーマ。
教科書レベルで完結する大問なので、正答率は高そうです。
予想通り、大問が増えただけ内容量・難易度ともに控えめになっているのだろうか。
(2) 難易度 ★☆☆
略。
大問2
(1) 難易度 ★☆☆
計算自体はとても簡単なので、設定を汲み取れるかどうか。
おそらくアの解答さえ間違えなければそのあとはスムーズに行けるはず。
★2にするか迷ったが、計算があまりにも簡単なので★1。
(2) 難易度 ★★☆
計算量も、方程式の作り方も(1)よりは難易度が上がる。
とはいえ、(1)ができるなら(2)もできるんじゃあないか?
ここからはあまり問題と関係ない話なのですが。
高校生になってこういう文章題解かされるのって、どうなんでしょうね。
数学の無機質、抽象的、一般的なとこがイケてるところだと思っていたので、
長々とした設定の文章題を出されると「うーん(笑)」首をかしげてしまいます。
どうしても「情報処理能力」という、数学の本質とは少し離れている能力を求められている気がするのです。
公務員試験やSPIなど就活には役に立ちますが・・・。
こういう大問を作っている方々の気持ちがあんまりわからないです。
大問3
(1) 難易度 ★☆☆
具体的な計算をするだけですね。
特筆事項なし。
(2) 難易度 ★★★
チャート等の問題集に載っていない類の問題ということでこの難易度にしています。
とはいえ、決して難しいことを訊かれているわけではないので、問題文の穴埋めをしながら理解を進めていきたいですね。
(ⅱ)以降はグラフを利用しながら解き進めましょう。
(ⅰ)をわけわからんまま解答していると(わけわからなくても正解はできてしまう)、
(ⅱ)は少し苦しいでしょう。
数2Bといえば積分の計算量で時間を取られるイメージが強かったので、積分がこのような形で出題されるのは意外です。
大問4
(1) 難易度 ★☆☆
格子点を数える数列の大問。
導入が非常に丁寧なので、間違いようがありません。
大問を通じて、とても簡単です。
(2) 難易度 ★☆☆
イージー。
(3) 難易度 ★★☆
ちょっと計算量が多い。
とはいえ方程式を立てるのも難しくない。
大問5
(1) 難易度 ★☆☆
統計の大問です。
統計は毎年似たようなことしか訊いてこないので安定するものですが、今年もおそらく例に漏れず。
(2) 難易度 ★★☆
文章が長いですが、別に読み込むのに時間がかかるわけでもなく淡々と基本事項を埋めていくだけです。
(3) 難易度 ★★☆
仮説検定が何をやりたいのかさえ分かっていればイージー。
大問通じて計算ほとんどいらない。
大問6
(1) 難易度 ★☆☆
ベクトルの大問です。とはいえ、問題後半はベクトルあんまり関係ない…。
どちらかというと”図形と方程式”なのかもしれない。
大問6で唯一ベクトルっぽい要素あるのが(1)です。
ここでミスると(2)以降もほぼ丸々おとします。
(2) 難易度 ★★☆
方程式とくだけー。
(3) 難易度 ★★☆
不等式解いたり因数分解するだけー。
だけとはいえ計算量はまあまあ。
大問7
(1) 難易度 ★☆☆
複素数平面の大問です。
統計と同様、あまり問題のバリエーションが多くないので点数が安定する単元のイメージです。
(2) 難易度 ★☆☆
教科書レベル、計算量ゼロ。
(3) 難易度 ★★☆
(ⅲ)以外は計算いらない、あるいは暗算レベル。
聞かれていることも教科書レベル。
大問4~7で一番当たりかも。
総評
・大問多い分、全体的に計算量控え目。
・計算はほどほどでいいので広く浅く、正しい理解が求められている印象。
・計算ガツガツの従来の数ⅡBとは明らかにテイストが違う。とはいえ、今年度の平均点が高ければ計算量は増やされるのだろう。
・時間は70 分あれば十分そう。大問4~7はそれぞれ5分で解けるサイズ。
・選択問題の難易度はほぼ差はありません。強いていうなら計算量・必要な時間の観点から
【難】4=6>5>7【易】
平均点を確認したら56 点だったので、今年度の路線で来年度も行きそうです。
(共通テストは60 平均を目指しているのでほぼ狙い通りのはず)
ひとつ気になったのは昨年度より差が開く科目になっていたことです。(標準偏差で判断してます)
計算量より理解度に焦点を当てると文系科目のように団子になりそうですが、逆なんですね。
確かに、計算量(時間)で点数を調整するのは簡単ですからね。
簡単に調整できるということは、おそらく点数のばらつきが少ないからでしょうし。
なんにせよ、数学ⅡBCが今までと別人なのがわかったのは収穫です。
数学については、塾の使用教材を変えることを割と本格的に検討する必要がありそうです。